Members理事・監事・アドバイザー
理事
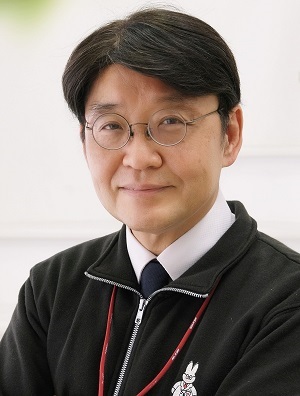
小澤 竹俊
代表理事
1963年東京生まれ。世の中で一番、苦しんでいる人のために働きたい と願い、医師を志し、1987年東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。 1991年山形大学大学院医学研究科医学専攻博士課程修了。救命救急センター、農村医療に従事した後、1994年より横浜甦生病院 内科・ホスピス勤務、1996年にはホスピス病棟長となる。2006年めぐみ在宅クリニックを開院、院長として現在に至る。「自分がホスピスで学んだことを伝えたい」との思いから、2000年より学校を中心に「いのちの授業」を展開。2013年より、人生の最終段階に対応できる人材育成プロジェクトを開始し、多死時代にむけた人材育成に取り組んでいる。

千田 恵子
業務執行理事
生まれてから最期を迎えるまで、そしてその後も、大切な存在と認め合える社会を目指し、小澤竹俊とともに2015年法人設立。尊厳を守り最期まで関われる人材の育成と、子どもの頃からの教育を通して自他をケアし合えるコミュニティの醸成に全国で取り組む。上智大学在学中、英語を母語としない子どもの学習支援が教育活動の原点。卒業後、企業で人材育成・新規事業開発・インド展開支援等、人が活きる仕組みづくりに従事するなか、父が難病ALSにて他界、3ヵ月後に母も旅立つ。自分が生きる意味を考えはじめたとき、このテーマを必要とする人へ届ける仕組みを必要としていた小澤と出逢う。これまで起きたすべてのことが今につながる想いで活動している。キャリアコンサルタント、准認定ファンドレイザー。

久保田 千代美
理事
1982年看護師免許取得後、JA広島総合病院在職中にホスピスケアに関心を持つ。1996年奈良に暮らしを移し、PTA活動をはじめとした地域貢献をする。2004年介護支援専門員、2006年より訪問看護に従事、2010年より看護学校専任教員となる。在職中に、全国の「暮らしの保健室」をテーマに調査研究、2018年大阪教育大学大学院にて学術修士取得。2019年独立して研究所を開設。研究・教育・対話を大切にした活動を行っている。2016年エンドオブライフ・ケア協会認定ファシリテーターとなり全国の教育機関、医療や介護施設で学習会や子どもから一般に向けていのちの授業を行っている。2020年第6回奈良のお薬師さん大賞(奈良県知事表彰)受賞。

濵田 努
理事
1978年鹿児島市生まれ。愛知医科大学医学部卒業、鹿児島大学大学院医学博士課程修了。専門は呼吸器内科・在宅医療。2014年からきいれ浜田クリニックの院長職。2020年3月~鹿児島大学病院 臨床教授として医学生指導も行っている。また院外においても認知症や在宅医療の取り組みや啓発活動など、地域包括ケアを推進する事業を行っている。現在はかかりつけ医として乳児から高齢者まで地域の方々へ医療を提供している。年間看取り件数約40件。エンドオブライフ・ケア援助士、ファシリテーター・いのちの授業認定講師の資格を持ち、死と向かい合う医療介護職の育成にも力を入れる。資格:臨床教授、医学博士、呼吸器学会専門医、認知症キャラバンメイト、認知症サポート医、禁煙学会認定医、内科認定医。

長野 宏昭
理事
1980年奈良県生まれ。岡山大学医学部卒業。中学生の時に大好きだった祖母を亡くし、いのちと向き合う現場での仕事を志す。2012年に沖縄へ移住し沖縄県立中部病院へ就職。在宅医療、ホスピスマインドを学ぶ仲間達と出会い、2023年いきがい在宅クリニックを設立。認定ELCファシリテーター・いのちの授業認定講師として子どもから大人まで幅広い層にマインドを紹介している。マインドを軸に地域をデザインする試みとして、シェアハウス型ホスピス「いきがいの家」、苦しみを抱えた人の居場所「よりどころ」を建設。琉球大学医学部非常勤講師として学生教育に力を入れ、答えのない心の問題について対話する学生サークル「ヨリドコロ」の外部顧問。趣味でヴァイオリン・ヴィオラ演奏を嗜んでおり、病院や地域でのコンサートも毎年開催している。 資格:総合内科専門医、呼吸器内科専門医・指導医、がん治療認定医 日本在宅医療連合学会評議員 他
監事

大西 純
2011年東日本大震災以降、銀行勤務の傍ら「会社人」より「社会人」との思いで平日夜や週末にプロボノ活動を開始。その後、非営利組織を中心に10数団体の伴走支援を実施。2018年から2年間は社会的な課題の解決に取り組む革新的な事業に対して資金の提供と経営支援を行うソーシャルベンチャー・パートナーズ東京(SVP東京)のパートナーとしてエンドオブライフ・ケア協会と協働、組織基盤強化などに取り組む。2013年妹を肺がんで亡くしたことから “エンドオブライフ”への関心を深める。1968年京都市生まれ、1991年大阪市立大学法学部卒業、三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行。2020年銀行を退職し独立。中小企業診断士、准認定ファンドレイザー。東京都在住。
研究員

武井 泉
大学院博士課程修了後、独立行政法人研究所、民間シンクタンク等を経て、現在事業会社にて地域連携・振興支援に従事。学生時代から開発途上国、特に農村部の貧困問題に関心を持ち、アジアやアフリカでのフィールドワークとともに経済・社会調査を行ってきた。2017年のシンクタンク在職中に、プロボノ活動としてELC活動に参加、エンドオブライフ・ケアやいのちの授業を学びながら以後主に教材開発や調査部分でボランティアとして活動に参画してきた。2019年にはカナダ・マニトバ大学のディグニティセラピーのワークショップに参加。その後、相次ぐ家族の看取りを経験し、ELC活動の重要性を再認識している。
アドバイザー

小野沢 滋
みその生活支援クリニック院長
1990年東京慈恵会医科大学 卒業。亀田総合病院 在宅医療部の初代医師に就任して以来、在宅医療の先駆者として長年、在宅医療と退院支援(在宅医療の受け入れ側と送り出し側)の二足の草鞋を続けてきた。「急性期病院において、病を得た一人ひとりに丁寧に介入し、その人が病とともにどのような人生を送りたいと考えているのかを引き出し、形にしていくこと」こそが、退院後、その人がより良い人生を送ることにつながる。「命を延ばすことが中心の医療から、一人ひとりの希望を中核に据えた医療への変革」を目指し、北里大学では入院前から退院後までを総合的に支援する「トータルサポートセンター」を率いて、看護師およびソーシャルワーカーを中心に、入院前の時点で退院後の生活までを見据えたアドバイスや情報提供を行ってきた。また、一人ひとりが希望した人生を送るための地域づくりの一環として、相模原町田地区介護医療圏インフラ整備コンソーシアム立ち上げにも従事した。

西川 満則
国立長寿医療研究センター病院緩和ケア診療部/エンド・オブ・ライフ(EOL)ケアチーム医師
1995年島根医大医学部卒。西尾市民病院、愛知国際病院ホスピス医、名大呼吸器内科医員などを経て、2000年より国立長寿医療センター(当時)に勤務。11年10月より現職。日本緩和医療学会暫定指導医、日本老年医学会専門医、日本呼吸器学会専門医。
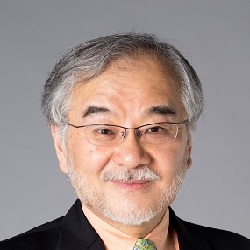
本間 正人
京都芸術大学教授、NPO学習学協会代表理事
「人は生まれてから最期の一瞬まで学び続ける存在である」という「学習学」の提唱者であり、「楽しくて、即、役に立つ」参加型研修の講師として最新学習歴を更新するアクティブ・ラーニングを25年以上実践。「研修講師塾」を主宰する。現在、京都芸術大学教授・副学長、NPO学習学協会代表理事、NPOハロードリーム実行委員会理事、松下政経塾研究主幹。コーチングやほめ言葉、英語学習法などの著書77冊。東京大学文学部社会学科卒業、ミネソタ大学大学院修了(成人教育学 Ph.D.)。ミネソタ州政府貿易局、松下政経塾研究主担当、NHK教育テレビ「実践ビジネス英会話」の講師などを歴任。TVニュース番組のアンカー、コメンテーターとしても定評がある。一般社団法人大学イノベーション研究所代表理事、一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会理事、一般財団法人自立学実践研究所理事、などをつとめる。

副島 賢和
昭和大学大学院保健医療学研究科 准教授、昭和大学附属病院内学級担当
東京都公立小学校教諭として25年間勤務。うち8年間品川区立清水台小学校(昭和大学病院内さいかち学級)担任。2014年4月より現職。病気のある子どもの教育の保障を研究(昭和大学附属病院内学級担当)。学校心理士スーパーバイザー。ホスピタルクラウン。横浜・北海道・福岡こどもホスピスプロジェクト応援アンバサダー。TSURUMI・東京こどもホスピスプロジェクトアドバイザー。NPO法人YourSchool理事。著書に『あのね、ほんとうはね』(へるす出版/2021年)。ドラマ『赤鼻のセンセイ』(日本テレビ/2009)のモチーフとなる。2011年『プロフェッショナル仕事の流儀』(NHK総合)に出演。

佐々木 淳
医療法人社団悠翔会理事長・診療部長
1973年京都市生まれ。手塚治虫のブラックジャックに感化され医師を志す。1998年筑波大学医学専門学群を卒業後、社会福祉法人三井記念病院に内科研修医として入職。2004年、東京大学大学院医学系研究科博士課程に進学。大学院在学中のアルバイトで在宅医療に出合う。「人は病気が治らなくても幸せに生きていける」という事実に衝撃を受け、在宅医療にのめり込む。2006年、大学院を退学し在宅療養支援診療所を開設。2008年、法人化。医療法人社団悠翔会・理事長に就任。2021年より 内閣府規制改革推進会議専門委員。

堀田 聰子
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授
京都大学法学部卒業後、東京大学社会科学研究所特任准教授、ユトレヒト大学訪問教授等を経て慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授(認知症未来共創ハブ代表)。博士(国際公共政策)。より人間的で持続可能なケアと地域づくりに向けた移行の支援及び加速に取組む。社会保障審議会・介護給付費分科会及び福祉部会において委員。アラン・ケレハー著(2022)『コンパッション都市―公衆衛生と終末期ケアの融合』慶應義塾大学出版会を共監訳、筧裕介著『認知症世界の歩き方』ライツ社(2021)を監修等。

宮崎 響
中学2年生
地域の中学校に通う14歳女子です。ラーセン症候群という先天的な病気を持って産まれてきました。 1歳までに5度の手術、7歳で気管切開と酸素、11歳で人工呼吸器をつけるようになりました。私は将来の夢があり、それに向かって勉強を頑張っています。私がやろうとしていることは誰もしたことがないので高い壁が立ち塞がっています。けど必ずぶち破って乗り越えます。そして私の後に続く人は平坦な道を歩けるようにしたいです。(2025年2月現在)
顧問
柏木 哲夫
当協会顧問、淀川キリスト教病院名誉ホスピス長
1965年阪大医学部卒。同大精神神経科に3年間勤務し、ワシントン大に留学。アメリカ精神医学の研修を積む。72年に帰国し、淀川キリスト教病院に精神神経科を開設。同時にターミナルケア実践のためのチームを結成。84年には日本で2番目となるホスピスを開設。副院長、ホスピス長を経て、1993年阪大教授に就任。淀川キリスト教病院名誉ホスピス長。2004年より金城学院大学長。07年から同学院長を兼務。13年より現職。日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団理事長。1994年日米医学功労賞、1998年朝日社会福祉賞、2004年保健文化賞受賞。
設立時賛同者
| 青木 淳 | 理学療法士 主任 |
|---|---|
| 赤澤 輝和 | 日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 |
| 秋山 博実 | 大曲厚生医療センター 緩和ケア科科長、秋田県緩和ケア研究会 副会長 |
| 朝比奈 完 | 睦町クリニック 院長 |
| 阿部 敦子 | 社会福祉法人 智泉会はあとぴあ 認知症対応型通所介護事業所 主任・生活相談員 |
| 阿部 信一 | 特別養護老人ホーム 千の杜(社会福祉法人 木犀会) 施設長 |
| 有永 洋子 | 東北大学大学院医学系研究科 地域がん医療推進センター 助教 |
| 石井 利明 | 石井医院 院長、浦和医師会 在宅理事 |
| 石渡 奈奈 | 在宅療養支援ステーション楓の風 湘南藤沢 訪問看護師 |
| 市原 利晃 | 秋田往診クリニック |
| 一瀬 恭子 | 緩和ケア認定看護師 |
| 泉山 典子 | 医師 |
| 井上 明美 | 医療法人つじ・クリニック つじ訪問看護ステーション 管理者 |
| 井上 貴弘 | 医療法人社団黎明会両国大塚クリニック 院長 |
| 猪口 寛 | 医療法人鵬之風いのくち医院 理事長、在宅ネットさが |
| 岩本 ゆり | 楽患ナース訪問看護ステーション 管理者、副理事長 |
| 遠藤 博之 | たんぽぽ診療所 院長、元 静岡済生会総合病院腎臓内科医師 |
| 大井 祐子 | 聖ヨハネ桜町ホスピス 医師 |
| 大石 春美 | 穂波の郷クリニック、緩和ケア支援センターはるか センター長 緩和ケアコーディネーター MSW |
| 大澤 匡弘 | 名古屋市立大学大学院 薬学研究科 薬剤師 |
| 大橋 英司 | 医療法人社団大橋内科胃腸科 理事長 |
| 大野 瑞穂 | 医療法人社団鶴友会 鶴田病院 薬剤部 薬剤師 |
| 岡本 拓也 | 洞爺湖温泉病院 ホスピス緩和ケア病棟 ホスピス長 |
| 小笠原 一夫 | 緩和ケア診療所いっぽ 院長 |
| 奥 玲子 | 合同会社アットアール代表 アットホームケア介護事業所 管理者 |
| 尾崎 雄 | NPO法人コミュニティケアリンク東京副理事長、元 日経新聞記者 |
| 小野 宏志 | 医療法人社団心 坂の上ファミリークリニック 理事長、第16回日本在宅医学会大会長 |
| 加治 陽子 | グリーフサポートせたがや 相談員 |
| 粕田 晴之 | 済生会宇都宮病院 緩和ケア科 診療科長 |
| 片山 典子 | 浅草医師会立訪問看護ステーション 看護師 |
| 加藤 春男 | 社会福祉法人 聖テレジア会 七里ガ浜ホーム 介護福祉士 |
| 嘉藤 茂 | 外旭川病院ホスピス長 |
| 金子 稚子 | ライフ・ターミナル・ネットワーク 代表 |
| 河 正子 | NPO法人緩和ケアサポートグループ 理事長、元 東京大学ターミナルケア看護学 講師 |
| 川野 京子 | 大分県立病院 緩和ケア室 がん性疼痛看護認定看護師 |
| 川村 和美 | シップヘルスファーマシー東日本(株) 教育研修部 部長 |
| 神崎 トモ子 | 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会 福祉推進課 課長補佐 看護師、主任介護支援専門員 |
| 北澤 彰浩 | 長野県厚生連佐久総合病院 診療部長 |
| 木村 幸博 | もりおか往診クリニック 院長、第17回 日本在宅医学会大会 大会長 |
| 串田 一樹 | 昭和薬科大学 地域連携薬局イノベーション講座 特任教授 |
| 工藤 純子 | ハートケア湘南台訪問看護リハビリステーション 管理者 |
| 久保田 千代美 | 学校法人栗岡学園阪奈中央看護専門学校 専任教員 |
| 倉田 理 | 一般社団法人 三重県介護支援専門員協会 副会長 |
| 栗山 登至 | 嬉野が丘サマリヤ人病院 医師、沖縄がん心のケア研究会世話人代表、元 琉球大学緩和ケア |
| 小鴨 覚俊 | 延暦寺一山恵光院 住職 |
| 小杉 寿文 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 緩和ケア科 部長・緩和ケアセンター長、日本ホスピス緩和ケア協会九州支部幹事、日本死の臨床研究会九州支部役員、日本尊厳死協会・さが理事、佐賀大学医学部臨床教授 |
| 小薮 基司 | 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 地域包括支援センター 主任介護支援専門員 |
| 小山 輝幸 | グリーンヒル泉・横浜 相談員 |
| 佐々木 淳 | 医療法人社団悠翔会 理事長 |
| 斎藤 如由 | 医療法人社団 五雲堂 斎藤醫院 院長、日本臨床倫理学会 評議員、筑後緩和医療研究会 世話人、福岡緩和ケア研究会 世話人 |
| 佐藤 美恵 | 訪問看護ステーションたが 訪問看護師 |
| 佐藤 恵 | 板橋区医師会在宅医会 会長 在宅医療連携拠点事業 事業責任者、佐藤クリニック院長 |
| 佐瀬 佳子 | 介護福祉士 |
| 沢田 亜幸 | 総合相模更生病院薬剤部 薬剤師 化学療法・在宅医療・外来化学療法・倫理委員会委員 |
| 佐原 まち子 | 公益社団法人日本医療社会福祉協会元会長、WITH医療福祉実践研究所代表理事、国際医療福祉大学元教授 |
| 志真 泰夫 | NPO法人 日本ホスピス緩和ケア協会理事長、日本緩和医療学会代議員・理事、筑波メディカルセンター病院在宅ケア事業長 |
| 清水 千世 | 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 副院長、第25回 日本死の臨床研究会 大会長 |
| 白井 三千代 | たんぽぽ訪問看護リハビリステーション 管理者 看護師 |
| 末永 和之 | すえなが内科在宅診療所 院長、元 綜合病院山口赤十字病院緩和ケア病棟 勤務、日本死の臨床研究会 前代表 |
| 鈴木 央 | 鈴木内科医院 院長、日本プライマリ・ケア学会 理事、日本在宅医学会 幹事、全国在宅療養支援診療所連絡会 副会長 |
| 柴田 実 | 東京看とり人プロジェクト・スーパーヴァイザー、聖路加国際大学 聖路加国際病院 チャプレン、フェリス女学院大学非常勤講師、横浜聖霊キリスト教会副牧師、日本スピリチュアルケア学会認定指導臨床会員・スピリチュアルケア師 |
| 下山 直人 | 東京慈恵医科大学麻酔科講座教授・緩和ケア室室長 |
| 白髭 豊 | 白髭内科医院 院長、日本在宅医学会 理事、日本医師会 在宅医療連絡協議会 メンバー |
| 白山 宏人 | 医療法人社団拓海会 大阪北ホームケアクリニック 院長 |
| 菅原 由美 | 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス・有限会社ナースケアグループ 代表 |
| 関根 和彦 | ベグライテン 世話人 |
| 関本 雅子 | 関本クリニック院長、元 六甲病院緩和ケア病棟(ホスピス)医長 |
| 副島 賢和 | 昭和大学大学院保健医療学研究科 准教授、元 昭和大学病院 院内学級「さいかち学級」 教師 |
| 高橋 美保 | ホームケアクリニックえん 看護師長 看護師・保健師・緩和ケア認定看護師 |
| 高見沢 重隆 | たかみざわ医院 理事長・院長、横浜市医師会理事 |
| 高宮 有介 | 昭和大学医学部医学教育学 講師、第20回記念日本緩和医療学会学術大会 大会長、大学病院の緩和ケアを考える会 代表世話人 |
| 玉井 照枝 | 東北公済病院 なんでも相談室 相談員 |
| 高橋 さつき | 総合病院勤務 看護師 |
| 高橋 悦堂 | 曹洞宗 普門寺 副住職、医療法人社団爽秋会 臨床宗教師 |
| 高山 由紀子 | 黒部市民病院 看護部 |
| 千葉 恭一 | ホームケアクリニックえん 院長 医師 |
| 千場 純 | 横須賀市医師会 在宅理事、三輪医院 院長 |
| 恒藤 暁 | 京都大学大学院医学研究科 集学的がん診療学講座 特定教授 |
| 鶴岡 優子 | つるかめ診療所 院長、自治医科大学 非常勤講師 |
| 髙村 一郎 | 髙村内科医院 院長 |
| 田中 牧子 | 看護師 |
| 田村 里子 | 一般社団法人 WITH医療福祉実践研究所 がん・緩和ケア部 |
| 寺口 浩子 | 聖ケ丘病院 訪問診療部 主任、 リンパ浮腫療法士(リンパ外来担当) |
| 寺嶋 吉保 | 徳島県立中央病院 臨床腫瘍科 部長、徳島県立三好病院 がん診療支援センター長、徳島県地域医療支援センター 副センター長、徳島緩和ケア研究会 代表 |
| 出水 明 | 医療法人出水クリニック 院長、岸和田市医師会 在宅担当理事 |
| 徳田 英弘 | ファミリークリニックネリヤ 院長、第18回日本在宅ホスピス協会全国大会 大会長 |
| 冨川 正子 | 長崎川棚医療センター 緩和ケア認定看護師 |
| 永井 康徳 | 医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 理事長、第1回全国在宅療養支援診療所連絡会 初代大会長 |
| 中澤 まゆみ | ノンフィクションライター |
| 中野 一司 | 医療法人ナカノ会理事長ナカノ在宅医療クリニック 院長、鹿児島大学医学部臨床教授 |
| 中野 しずよ | 認定NPO法人市民セクターよこはま 理事長 |
| 中野 徹 | 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会 副主幹 |
| 中林 咲子 | 在宅療養支援ステーション楓の風やまと 訪問看護師 |
| 新堀 いずみ | あそかビハーラクリニック 看護部長、日本写真療法家協会 理事 |
| 西国領 俊子 | 西国領歯科医院 日本障害者歯科学会認定医 歯科医師 |
| 西村 幸祐 | JA岐阜厚生連 岐北厚生病院緩和ケアセンター長、第39回日本死の臨床研究会年次大会 |
| 二ノ坂 保喜 | にのさかクリニック院長、「バングラデシュと手をつなぐ会」代表 |
| 年代 眞規子 | 三浦市立病院 看護部 看護助手 (緩和ケア•地域包括ケア 病棟) |
| 野尻 明子 | 熊本保健科学大学 リハビリテーション学科生活機能療法学専攻 講師 |
| 林 章敏 | 聖路加国際病院 緩和ケア科医長、元 淀川キリスト病院 消化器内科・ホスピス、日本バプテスト病院 ホスピス長・訪問診療部長 |
| 英 裕雄 | 医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 理事長、第2回全国在宅療養支援診療所連絡会 大会長 |
| 濱田 昇 | 国立病院機構 南岡山医療センター呼吸器アレルギー内科 医師 |
| 原澤 慶太郎 | 亀田総合病院 在宅医療部 医師 |
| 原田 脩平 | 公設宮代福祉医療センター リハビリテーション室 理学療法士 |
| 原田 美雪 | 倉敷中央病院看護師長/緩和ケア認定看護師 |
| 廣田 芳和 | 在宅療養支援ステーション楓の風 横浜あさひ 管理者 看護師 |
| 廣橋 猛 | 永寿総合病院 医師、元三井記念病院緩和ケア 医師 |
| 蘆野 吉和 | 北斗病院 在宅緩和療養センターセンター長・在宅医療科 部長、NPO法人日本ホスピス・在宅ケア研究会副理事長、日本在宅医療学会理事、日本死の臨床研究会常任世話人、在宅医療推進会議(国立長寿医療センター)委員、日本緩和医療学会代議員、第16回日本緩和医療学会学術大会会長 |
| 平田 麻紀 | まるクリニック訪問看護ステーション 看護師 |
| 深尾 一絵 | 恵生会橋本クリニック 医師 |
| 福島 優子 | 在宅療養支援診療所 つつみクリニック 看護師 |
| 藤井 義博 | 死の臨床研究会 国際交流委員会委員長 |
| 藤田 敦子 | NPO法人千葉・在宅ケア市民ネットワークピュア代表、日本ホスピス・在宅ケア研究会 理事 |
| 藤本 麗子 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 緩和ケアチーム専従看護師 |
| 北條 宏美 | 在宅療養支援ステーション楓の風やまと 管理者 |
| 堀越 由紀子 | 東海大学健康科学部社会福祉学科 教授 |
| 紅谷 浩之 | オレンジホームケアクリニック 医師 |
| 本家 好文 | 広島県緩和ケア支援センター長 |
| 前野 宏 | ホームケアクリニック札幌 院長、元東札幌病院緩和ケア病棟長 |
| 松尾 大志 | マーガレットクリニック 院長 |
| 丸山 善治郎 | まるクリニック 院長、元 いばらき診療所みと 院長、水戸在宅ケアネットワーク代表 |
| 三浦 靖彦 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 部長 |
| 三戸部 聖子 | 東葛病院 医師 |
| 宮下 光令 | 東北大学医学部保健学科看護学専攻 教授、日本緩和医療学会 理事・代議員 |
| 村上 望 | 厚生連高岡病院 緩和ケア外科 診療部長 |
| 村松 真澄 | 札幌市立大学看護学部准教授 |
| 森田 昌子 | NPO法人野のゆりホーム |
| 泰川 恵吾 | 医療法人鳥伝白川会 ドクターゴン診療所 理事長 |
| 矢津 剛 | 矢津内科消化器科クリニック 理事長・院長、元 京都医師会理事 |
| 矢田 俊量 | 三重県桑名市善西寺 住職 |
| 山岡 憲夫 | 医療法人カーサミア やまおか在宅クリニック 院長、大分大学医学部 臨床教授 |
| 山口 高秀 | 医療法人おひさま会 理事長、やまぐちクリニック院長、一般社団法人LINK代表 |
| 山口 龍彦 | 高知厚生病院 院長、日本ホスピス・在宅ケア研究会 理事、高知大学医学部 血液・呼吸器内科学教室 臨床教授 |
| 山崎 章郎 | 聖ヨハネホスピスケア研究所 所長、桜町病院 聖ヨハネホスピス 顧問、ケアタウン小平クリニック 院長、日本ホスピス緩和ケア協会 常任理事、日本死の臨床研究会 代表世話員、日本緩和医療学会 代議員 |
| 山田 祐司 | 愛和病院 院長、日本ホスピス緩和ケア協会関東甲信越支部 理事 |
| 山名 保則 | 八戸在宅クリニック 院長 |
| 山本 五十年 | 医療法人救友会 理事長 湘南真田クリニック 院長、元 東海大学医学部救命救急・地域医療連携講座特任准教授 |
| 横山 幸生 | かとう内科並木通り診療所 在宅介護支援センターなみきケアマネジャー |
| 吉澤 明孝 | 要町ホームケアクリニック院長、要町病院 副院長、東京医科歯科大学大学院非常勤講師、京慈恵会医科大学腫瘍血液内科非常勤臨床医長(緩和ケアチーム) |
| 吉森 仁美 | 日本調剤 尾山台南口薬局 在宅専任薬剤師 |
© End-of-Life Care Association of Japan

